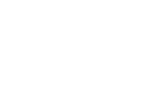熱が出ると、身体がだるく、頭もぼーっとして辛いですよね。
そもそも、なぜ私たちは風邪を引くなどすると発熱するのでしょうか?
ここでは、症状ごとの発熱のメカニズムについて解説します。
なぜ人は発熱する?その理由とは?
発熱のメカニズムについて、ケースごとに紹介します。
1.感染症の場合
体内に感染症などのウイルスが入ってきたら、免疫活性食細胞がウイルスを食べるように取り込み、処理します。
その後、免疫活性食細胞は低分子のたんぱく質である「サイトカイン」を作り出します。
サイトカインは、血流に乗り、脳に流れ着きます。
その後サイトカインは「メディエーター」と呼ばれる物質を作り、視床下部へと情報を伝えます。
このメディエーターが届くことによって、視床下部の体温調整中枢は「発熱しろ」という命令を身体の各部に出すのです。
このようにして、私たちの体温は上がります。
では、なぜ発熱するのか。
これは体温が高くなることにより、ウイルスなどの病原体の活動が弱まり、免疫細胞の動きが活発化するからです。
そのため、安易に熱を下げてしまうと、ウイルスの働きを助けてしまうことがあり、逆に完治まで時間がかかってしまう恐れがあるため、注意が必要。
感染症などの場合、発熱は短期間で、2週間以内に治癒するケースが多いです。
2.アレルギー性疾患・膠原病の場合
人間は、細菌やウイルスなど人体に悪影響を与える異物が侵入してきたとき、これを撃退する仕組みをもち、これを免疫反応といいます。
しかし中には、人体に影響を及ぼさないほどの微量のウイルスや細菌にも過剰に反応してしまい、逆に自らの身体にダメージを与え、発熱してしまうことがあります。
これがアレルギー反応です。
膠原病も同じような仕組みで、発熱します。
3.悪性腫瘍の場合
白血病や悪性リンパ腫など血液の腫瘍にて、比較的発熱が起こりやすいです。
悪性腫瘍による発熱の原因・仕組みはさまざまで、腫瘍そのものから発熱を促進するたんぱく質が作られたり、腫瘍細胞が壊死した際、細胞死したあと免疫細胞が掃除するときに発熱する物質を出したり、また腫瘍の悪化が進行し、体力が衰えたところに、ウイルスや菌が入り込み、感染症にかかり1.のような仕組みで発熱したりすることもあります。
4.うつ熱の場合
日射病や熱射病など、外気の温度が高く、身体が上手く熱を放散できないときに発熱します。
この場合、すぐさま体温を下げる必要があり、風通しを良くしたり、クーラーや扇風機などを使って涼んだりすることが大切です。
うつ熱は、感染症などによる発熱とは仕組みが異なるため、解熱剤は有効ではありません。
それどころか、副作用が起きる危険性もあります。
特に体温調節機能が不十分である高齢者や子どもはうつ熱を発しやすいので、注意が必要です。
平熱が低い人の原因とは?
近年、公共交通機関の急速発展により、生活環境の利便性が大幅に向上している影響で、低体温の症状に頭を抱えている人も増えてきています。
たとえば、一昔前に比べエスカレーターおよびエレベーターやバス・電車・タクシーといった公共交通機関などが、目まぐるしい発展を遂げています。
その結果、毎日の運動量が激減したことにより、現代人の基礎代謝量や筋肉量などが減少傾向にあります。
基礎代謝量や筋肉量が減少することは、体内にて熱を生み出す機会が少なくなってきていることに直結します。
つまり、生活環境の利便性向上が、低体温の原因だと考えられているのです。
また、低体温は生活環境の利便性向上以外にも、さまざまな原因・ポイントが関与しています。
低体温の原因に直結するポイントの具体例については以下のとおりです。
■低体温の原因
・エアコンの稼働により体内の温度調整機能が上手く働かなくなった
・締め付けの強い洋服による血行不良
・露出度の高い洋服を着用することによる体全体の冷え
・季節を問わず、アイスクリームやカキ氷などを口にする
(冷たい食べ物は体全体を冷やす効果がある)
仮に、自身の体温が低いことについて悩んでいる人は、前述の原因を念頭に置いたうえで、まずは、生活スタイルの改善を試みてはいかがでしょうか。
発熱の仕組みは病気ごとに異なる!
発熱の仕組みについて解説しました。
私たちの体温は、ウイルスや細菌などの病原体の侵入や外的要因による体温調節機能の不具合など、さまざまな要因で上がります。
体温が上昇すると苦しいですが、免疫細胞が活発になり、ウイルスが抵抗力を弱めるといった良い側面もあります。
発熱時は、どのような仕組みの発熱かを理解したうえで、適切な処置をとれるとよりいいでしょう。
当社では自動検温・消毒噴射ができる自動検温器を販売しています。
自動検温器購入についてはコチラからご覧ください。