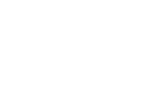非接触検温器の購入や利用を考えている人の中には、「そもそも非接触検温器って、なんで身体のどこにも触れることなく、体温を測れるのだろう?」と疑問を持っている人も少なくないと思います。
なぜ非接触検温器は、体温を計測できるのか?
ここでは、非接触検温器の仕組みについて説明します。
非接触検温器の仕組みとは?
非接触検温器が、身体に触れることなく体温を測れるのは、私たちが発している“赤外線”をキャッチしているからです。
赤外線とは、私たちには目に見えない光(電磁波)を指します。
すべての物体は、-273.15度という絶対零度と呼ばれる温度より高ければ、赤外線を放射しています。
まず対象が放出する赤外線を、赤外線集光レンズを用いて集光します。
検出できる波長帯の赤外線を集めることで、測定精度を向上させられます。
次に、集めた赤外線を、サーモパイルと呼ばれる電気部品を使って、電気信号に変換し、出力します。
その後、増幅アンプを使って、サーモパイルから発せられた電気信号を増幅します。
これによって、より高精度の測定が可能になります。
最後に、赤外線と補正のための放射率を用いて、温度を計測します。
放射率は物体ごとに一定の値をとる、物体の表面温度に対して放出される赤外線の割合のことで、サーモパイルが変換して出力した電気信号から検出した赤外線量と、あらかじめ測定しておいた放射率を用いて計算することで、温度を測ることができます。
簡単にいうと、物体が出す電磁波の性質は、温度によって変わるため、体温が測定できるということです。
市場に出回っている非接触検温器のほとんどは、この赤外線感知型です。
他にも、黒体放射と呼ばれる原理を使用する非接触検温器も存在します。
非接触検温器のデザインは、遅くとも19世紀後半には存在していたといわれています。
あらゆるものに触れることなく温度を測れる非接触検温器は、食品工場や半導体の製造現場などさまざまなシーンにて用いられています。
サーモグラフィーも同じ原理です。
サーモグラフィーは、対象から放射される赤外線を分析して、分布図・画像としたものです。
新型コロナウイルスの蔓延により、現在は、空港や商業施設等でも見かけるようになりました。
人体などが赤や青、黄色、緑などに色分けされている画像を見たことがある人も多いと思います。
非接触検温器が使用されている場所を紹介
新型コロナウイルスの感染拡大が世界規模にて大きな問題となっているなか、あらゆるシチュエーションにおいて非接触検温器の導入が推奨され始めています。
非接触検温器は、主に不特定多数の人が一度に集まる場所・シチュエーションにて幅広く活用されています。
新型コロナウイルスをはじめとした感染症の症状として、「発熱作用がある」といったポイントがあげられます。
発熱の症状にともなう感染症の疑いがある人については、できる限り店内や施設内に入ることを防止したいところです。
そのため、利用者の多くが集まる場所では検温の実施を徹底したうえで、発熱している利用者を店内・施設内に入れないようにするためにも、非接触検温器は、各店舗・施設の出入り口付近に設置することを意識しましょう。
また、「非接触検温器の基準数値を超えた場合は入場・入館をお断りさせていただきます。」などの文言が書かれた張り紙を掲載することで、「入場・入館を拒否する」といった行為にともなう利用者とのトラブル発展リスクを解消させる効果が期待できるでしょう。
なお、非接触検温器が使用されている場所の具体例については以下のとおりです。
■非接触検温器が使用・導入されている場所
・各種事務所やオフィスの受付
・商業施設の出入り口付近
・飲食店および小売店の出入り口付近
・トレーニングジムの出入り口付近
・セミナー/イベントの会場
・保育園/幼稚園/学校の校門付近および各教室の出入り口付近
・公共交通機関の出入り口付近
・病院/介護施設の受付
など
当サイトではオススメの非接触型体温計の種類と特徴についても記載しております。
詳しくはこちらの正確さでおすすめの7つの非接触体温計・AI検温器の記事をご覧ください。
非接触検温器は人や物に触れることなく、温度を測れるというメリットがあるものの、デメリットも存在します。
まず屋外や外気等の影響を受けやすいので、16~40度といった適温の室内でしか使用することができません。
また脇や口にはさんで用いる実測式の体温計に比べると、誤差が出やすい傾向にあります。
非接触体温計を使用することのメリットについて気になる方は、こちらの非接触体温計の5つのメリットの記事を併せてご覧ください。
非接触検温器を利用する前に、まず仕組みを理解しておこう!
非接触検温器の仕組みは理解できましたか?
非接触検温器は、すべての物体が発する赤外線とあらかじめ測定しておいた放射率を用いて計算することで、温度を算出することができます。
触れることなく、即座に体温を測定できるため便利ですが、屋外では利用しづらいなどのデメリットも存在します。
まずどのような仕組みで動いているのかを知り、適切な使い方をしていきましょう!